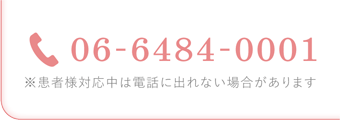子宮がんは、女性に発症するがんの一つです。かつては中高年層に多く見られる病気とされていましたが、近年では20代後半から40代の比較的若い世代でも増加傾向が見られます。日本では毎年1万人以上が新たに診断されており、決して珍しい病気ではありません。
子宮がんの特徴は、初期段階では自覚できる症状がほとんどないことです。進行してから気づくケースも多く、発見の遅れが治療の選択肢や予後に大きく影響します。そのため、普段から体の変化に意識を向けることが大切です。
本記事では「子宮がんの初期症状」について解説します。子宮がんに関する理解を深めることが、日常生活における小さな変化に気づき、早期発見へとつながります。
子宮がんとは?
子宮がんは、子宮の入り口にあたる部分に発生する悪性腫瘍です。子宮がんは大きく二つに分けられ、出口付近にできる「子宮頸がん」と、内側にできる「子宮体がん」があります。子宮は赤ちゃんを育む子宮体部と、膣につながる子宮頸部から成り立っています。特に外界に接する頸部は感染や刺激を受けやすく、細胞の異常が起こりやすい部位とされています。
子宮がんは突然「がん」になるわけではなく、まず「異形成」と呼ばれる前がん病変が現れ、数年から十数年をかけて「上皮内がん」、さらに進行すると「浸潤がん」へと発展します。組織のタイプは「扁平上皮がん」と「腺がん」に大別されます。日本では、扁平上皮がんが多い傾向がありますが、近年では腺がんの割合も増えており、検診では発見しにくいことから、特に注意が必要とされています。
子宮頸がんとは?
子宮頸がんは、子宮の出口付近にある頸部に発生します。主な原因は、「ヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染」で、性交渉によって感染が広がることが知られています。20代後半から30代の比較的若い世代でも発症することがあり、前がん病変から数年〜十数年をかけて進行するのが特徴です。検診での細胞診やHPV検査で早期発見が可能で、ワクチンによる予防効果も期待できます。
子宮体がんとは?
子宮体がんは、子宮の内側を覆う子宮内膜から発生します。主な原因は、「女性ホルモン(特にエストロゲン)の影響」が大きく、閉経前後から50〜60代にかけての女性に多くみられます。肥満や糖尿病、未出産歴なども要因とされます。子宮体がんは、「不正性器出血」(特に閉経後や月経周期外の出血)という症状で気づかれることが多く、頸がんと違ってワクチンでの予防はできません。そのため、生活習慣の見直しや、症状に気づいた時点で早めに受診することが大切です。
子宮がんの初期症状として現れるサイン
初期の段階では無症状であることが多いですが、進行の始まりに見られるサインとして「月経時以外の不正出血」や「おりものの変化」が挙げられます。おりものに血が混じる、膿のように濁る、量が増える、あるいはにおいが強くなるといった変化は注意が必要です。
さらに病状が進むと「下腹部の痛み」や「腰の重い感じ」といった症状が現れ、より進行すると腫瘍が膀胱や直腸に及ぶことで「排尿障害」「血尿」「血便」などの症状につながることがあります。
HPV感染と子宮頸がんの関係
子宮頸がんの発症に関わる要因の一つが、ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染です。特に発がん性の高い型に持続的に感染すると、細胞の異常が進行しやすくなります。多くの場合は免疫の働きによって自然に排除されますが、一部は体内に残り続け、がんに進展するリスクを高めます。発症を防ぐためには、感染リスクを正しく理解したうえで、予防法や定期的な検診を積極的に取り入れることが重要です。
喫煙は子宮頸部の細胞に悪影響
HPV感染以外にも、子宮頸がんの発症を後押しする要因があります。喫煙はその代表であり、たばこに含まれる有害物質が子宮頸部の細胞に悪影響を与えることでリスクを高めます。
また、出産回数が多い女性や、免疫力の低下も重要な要因であり、免疫抑制剤を使用している人や基礎疾患を持つ人はリスクが上昇します。
定期検診の役割と早期発見の重要性
子宮がんは前がん病変の段階で発見できる数少ないがんです。異形成や上皮内がんの段階で見つかれば、進行を食い止めることができます。症状がなくても検診を受けることで、目に見えない細胞の異常を早期に捉えることが可能です。
検診では細胞診やHPV検査が用いられ、必要に応じて拡大鏡による精密検査や組織診も行われます。20歳を超えた女性には定期的な検診が推奨されており、症状がなくても継続的に受けることが確実な予防行動です。
治療法と予防の取り組み
初期の段階で見つかれば、子宮を温存できる治療が可能です。円錐切除術など比較的負担の少ない方法で完治を目指せる場合があり、妊娠や出産の希望を持つ女性にとっても大きな意味を持ちます。進行が進むと子宮全摘出、放射線治療などが必要になり、生活や将来に大きく影響します。
予防の観点では、HPVワクチンの接種が大きな役割を果たします。高リスク型への感染を防ぐ効果があり、特に若年層での接種が推奨されています。成人女性に対しても一定の予防効果があるとされ、検診と組み合わせることで発症を防ぎ、健康を守る力になります。