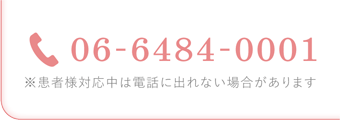おりものの変化は女性の体のサインとして重要な意味を持ちます。量が多い、色が変わった、においが気になるなど、日常的な変化の中には健康な範囲のものもあれば、病気の可能性があるものもあります。
本記事では、「おりものの量が増える原因」や「おりものが異常と考えられるケース」「受診が必要なサイン」について解説します。
おりものとは?体にとっての役割と正常な状態
おりものとは、子宮や膣(ちつ)からの分泌物で、古くなった細胞や白血球、細菌などが混じりあった粘性のある液体のことです。生理周期によって量や状態が変化し、女性の体を守る役割を果たしています。主な働きは膣内の潤滑と自浄作用で、細菌の侵入を防ぎ、健康な環境を保つことです。正常なおりものは、無色〜半透明、白色または黄白色で少し粘りがあり、においはほとんど感じません。
量や質はホルモンバランスによって変動します。排卵期には透明で粘りが少なく、量が増える傾向があります。妊娠中も増えることが多く、これは体の自然な反応です。正常範囲のおりものは心配不要ですが、色やにおい、質感の変化、かゆみや痛みを伴う場合は異常の可能性があります。
おりものの量が多くなる主な原因
おりものの量が増える原因はさまざまです。
生理周期の排卵期や妊娠初期、更年期前後など、女性ホルモンの変化が直接関わる場合があります。排卵期には卵子が精子と出会いやすい環境を作るため、粘度が低く量が多いおりものが分泌されます。妊娠中は血流量やホルモンの影響で膣分泌液が増加します。
精神的ストレスや過労、睡眠不足といった生活習慣の乱れもホルモンバランスを崩し、量が増える原因となります。また、性感染症や細菌感染など病気によっても増えることがあり、この場合は色やにおい、かゆみなど他の症状を伴うことが多いです。原因が生理的なものか病的なものかを見極めることが大切です。
異常なおりものに見られる特徴
異常なおりものは、色・におい・質感・量のいずれかに変化が現れます。黄色や緑色、茶色、灰色など通常とは異なる色調は細菌感染や炎症を示唆することがあります。魚のような強いにおいは細菌性膣症の可能性があり、カッテージチーズのような塊のある場合はカンジダ膣炎が考えられます。泡状や膿のような質感が見られる場合はトリコモナス膣炎や細菌性膣炎を疑うサインです。
また、量が急に増えた、下着がすぐに湿る、夜間も分泌が多いなどの変化も異常の一つです。かゆみ、灼熱感、下腹部の痛みを伴う場合は特に注意が必要です。これらの症状がある場合は自己判断せず、早めの婦人科受診が望まれます。
おりものの異常から考えられる病気の可能性
おりものの異常は、婦人科疾患や性感染症のサインであることがあります。病気の可能性を早期に見つけるためにも、症状がある場合は必ず受診することが重要です。
カンジダ膣炎は白くポロポロしたカッテージチーズ状のおりものと強いかゆみが特徴です。細菌性膣症では灰白色で悪臭を伴うことが多く、膣内の善玉菌が減少して雑菌が増えている状態です。トリコモナス膣炎では黄緑色で泡立ったおりものが出ることがあります。子宮頸がんや子宮体がんなどの悪性疾患でも、おりものの色やにおい、血が混じるなどの異常が現れることがあります。また、クラミジアや淋菌感染症など性感染症も異常なおりものの原因となり、放置すると不妊や骨盤痛のリスクがあります。
受診を検討すべきサインとタイミング
おりものの変化が一時的で他の症状を伴わない場合は、経過を観察しても問題ないことがあります。しかし、色やにおいの変化が続く、量が急に増える、かゆみや灼熱感、痛みがある場合は、早めの婦人科受診が推奨されます。
不正出血や月経異常、下腹部痛などを伴う場合は、重篤な病気が隠れている可能性もあります。性感染症が疑われる状況も受診のきっかけになります。特に妊娠中は感染が母体や胎児に影響することがあるため、自己判断せず必ず医師の診察を受けましょう。受診の目安を知っておくことで、安心して日常を過ごすことができます。
婦人科で行われる検査と治療方法
婦人科では、おりものの異常がある場合は問診で症状の詳細や経過、生活習慣、性交歴などを確認します。その後、膣内の分泌物を採取して顕微鏡検査や培養検査を行い、原因菌や炎症の有無を特定します。性感染症が疑われる場合は、血液検査や尿検査を併用することもあります。
治療は原因によって異なり、細菌感染には抗生物質、真菌感染には抗真菌薬を使用します。性感染症の場合はパートナーの同時治療が必要になるケースもあります。悪性疾患が疑われる場合は、さらに精密検査や画像検査を行い、手術や放射線治療などが検討されます。早期に原因を突き止めることで、治療期間の短縮や再発予防につながります。
日常生活でできるおりもの異常の予防とセルフケア
おりもの異常を予防するためには、膣内環境を整えることが大切です。通気性の良い下着を着用し、締め付けすぎない服装を心がけます。石けんやボディソープで膣内を洗いすぎると善玉菌まで減ってしまうため、外陰部はぬるま湯で優しく洗う程度が適切です。ストレスや睡眠不足はホルモンバランスを乱し、おりものの変化を招くため、十分な休養とバランスの取れた食生活を意識しましょう。定期的な婦人科検診も、症状が出る前に異常を発見する有効な手段です。日頃から体の変化に敏感になり、異常を感じたら早めに専門医へ相談することが、健康維持への第一歩となります。